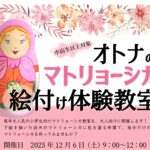ロシアのタトゥー文化
一般向け文化講座「はこだてベリョースカクラブ」今年度第4回目の講話内容です。
テーマ:ロシアのタトゥー文化
講 師:イリイナ・ソフィア(講師)
タトゥーというと、囚人などが入れる下品なイメージがあるかもしれませんが、今日は歴史的観点からおもしろい話まで、いろいろ紹介したいと思います。
通常、タトゥーは入れた人が亡くなれば残りません。つまり人の寿命に限られるものですが、5300年前のエジプトのミイラやアルプス山脈の氷河で発見された人など古代の人も入れており、その歴史は6000年におよびます。腰や背中など、傷みを生じやすい部分に入っていたため、針治療のような医療的な意味があったかもしれません。
ロシアの北東端に住むチュクチ人の女性は、鼻筋に沿っておでこにつながるタトゥーが入っていて、年とともに薄くなります。紀元前6~3世紀のパジリク文化では、南シベリア・アルタイ共和国にあるパジリク古墳群からタトゥーを持つ多くのミイラがほぼ完全な状態で発見されています。永久凍土の中で自然に保存されたものです。
90年代、アルタイでもう一つのミイラの発見がありました。「ウコクの王女」と呼ばれるもので、見事なタトゥーが入っていますが、模様の意味はわかっていません。そのほか、ハカス共和国のタシュティク文化のミイラがエルミタージュ美術館に所蔵されています。カスピ海と黒海に近いダゲスタン共和国では現在、少数民族に伝統が残っています。女性は若い年齢の時にタトゥーを施されますが、今では年を取って模様の意味を覚えていないそうです。たいていお守りの意味を持っていたようです。
そのほか、近現代では船乗り、軍人、囚人などにタトゥーを入れた人が多いですが、日本の鮮やかで美しい刺青と違って、ほとんどが黒色で様々な意味を持つものが多いです。徴兵者は左腕に十字の印だったり、逃亡者を確認するためのものであったり、ソ連時代にはレーニンやスターリンの顔を体に彫っていると撃たれない、などという迷信もありました。
※ 様々なタトゥーの画像を見ながら、その意味するところを解説しました。講話はロシア語で行われ、イリイン・ロマン准教授が通訳しました。